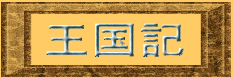
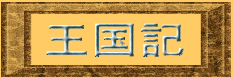
第2話
レイアード国クレスター城。
城内はグレース国の使者の出迎えの準備で、女官達が慌ただしく動いていた。
ヘンリー王子も同行していることを知らされ、城内の緊張は増し、お互い少しでも自分の仕事の邪魔をされようものなら、瞬時にひっつかみ合いの騒動が起こりそうな、そんな殺気が城内に渦巻いていた。
その殺気とは、まるで無縁の空間のような、場所が一室。
そこでは女官達は慌てるふうもなく、静かに、しかし迅速に王子の支度を整えていた。
ユリウス王子。デューク国王嫡男、第二子にして、ただ一人の王位継承者。
柔らかく金色に波打つ髪は、女官に丁寧に梳(す)かれてあり、華奢(きゃしゃ)な身体は正装であるシルクのブラウスに、濃紫の上下つなぎの上着で纏(まと)われていた。
今まで黙って女官達のされるままになっていたユリウスだが、おもむろに口を開いた。
「イオナ」
「はい」
イオナと呼ばれた老女は、王子付きの女官長だった。女官長は王子の支度の出来具合を入念に確認していたが、それを中断してユリウスの左後ろに控えた。
ユリウスはとても穏やかに微笑んでいた。王子は齢15才。まだ少年のあどけなさを残していて、一度でも彼の笑顔を見た者は、天使とはかくありきと、皆口を揃えて賞賛した。
「義兄上(あにうえ)になる方は、どんな人だろうね」
「さあ、お噂では聡明でお優しい人柄だとお聞きしておりますが」
その言葉を聞いて、ユリウスの笑顔は輝きを増した。
「ああ、早くこちらに来られないかなあ。早くお会いしたい」
無邪気な彼の様子は、周りの者達皆の心を和ませた。そして、その場にいた
女官は全てこう思ったに違いない。いかにヘンリー王子が立派で聡明な人物だとしても、このユリウス様には及ぶまいと。いつも自分たちに優しく接し、怒った顔など一度も見せたことがないユリウス。彼女たちは、彼に仕えることをこの上ない喜びに感じていた。
そしてヘンリー王子には負けるまいと、さらにユリウスの身支度に力を入れた。
馬車に揺られること数時間。ヘンリー王子の一行はようやクレスター城の門をくぐった。
薄暗い門道を通り抜けて陽のもとへ出たとき、突然辺りの空気が変わった。
馬車内にいてもはっきりとわかる大きな振動が、ヘンリー王子を包んだ。
窓の外を見やると、道端をうめつくした民衆の群がヘンリー王子の視界に映った。
皆一時にわっと歓声を上げ、その場は異様な程の熱気を帯びていた。
はじめ歓声は統一されていなかったが、次第にヘンリー王子の名前を呼ぶ声が理解できるようになり、ついには一定のリズムで連呼されることになった。
ヘンリーはまんざらでもなさそうに、彼らの声に応えるように右手をかざした。
まるでこの光景は、自分が本当に王になって民に迎え入れられているような錯覚を誘い、ヘンリーはしばしの間その余韻に浸った。
(ふふ、こんな光景、もうすぐ本当のことになる・・もうすぐだ)
そうして馬車は城下町を通り抜け、確実に王国の核へと進んで行った。
城に到着したヘンリーは数名の供の者を連れて、丁重な扱いを受けて円卓の間へ案内された。
それは150インチ四方の正方形の形をした部屋で、四隅と円卓には赤と白のバラが飾られ、南方に用意されたヘンリーの席の左向こうには、一枚の大きな聖母像がかけてあった。
壁や天井は明るいクリーム色、大きな窓からは心地よい日差しが入ってきて、この部屋はとても落ち着きのよい、感じのいい間だった。
そう待たされることなく、デューク王が数人を従えてやってきた。
「お待たせした」
肩幅のあるやや筋肉質の上背のある身体、威厳ある風格と鋭い眼光だが、不思議と威圧感を与えることはない。ヘンリーの、デューク王の第一印象はそんな感じだった。
ヘンリーは何か得るモノはないかと食い入るようにデュークを観察していたが、大きな手を差し出されて慌てて立ち上がり、自分も手を差し出した。
「失礼いたしました。この度は突然訪問してしまい、申し訳ありません。
不作法者と心得ておりますが、1日でも早く姫のお姿を拝見したく思い、
また、義父上様にもご挨拶したいとはやる心を抑えられずに、このような行為に出てしまいました。どうか、非礼をお許し下さい。」
「いやいや、そのような言葉をもらって、ローラも果報者よ。
安心して送り出して行ける。今、娘と息子を中に呼ぼう」
デュークが右に控えていた付き人に合図をすると、その側近は一礼してドアに向かい、片方の扉をゆっくりと引き開いた。
「失礼いたします」
大きくはないがよく通る女性の声が室内に響き、静かにローラとお付の侍女2人が入ってきた。ローラは噂に違わない美少女だった。色白の整った顔立ち、背中の中程まである金色の柔らかな巻き毛。線の細い身体。艶やかな美しさではなかったが、可憐な、保護意識を強く感じさせる少女だ。
まさに美男美女のカップルに相違なく、ヘンリーは一目で彼女を気に入った。
ローラは少し恥じらうように、目を伏せてヘンリーの左向かいに位置取った。
デュークがローラを紹介すると、ローラは頬を少し赤らめて会釈した。
「このような美しい女性に会ったことがありません。このような方を妻にできるとは、
本当に私は国一番の幸福者です」
「そのようなお戯れを・・」
ローラは消え入りそうな声で答えた。周りの者達は微笑ましく2人のやりとりを見ていた。
その場が和やかな雰囲気になっていると、室外からまた声がした。
「ユリウスでございます。失礼いたします」
声に反応して、ヘンリーは何気なくそちらに目をやった。1人の少年と、5人の騎士風情の者が室内に現れた。
ユリウスを一目見て、ヘンリーは内心冷笑した。
(なんだ、ただの小倅か、警戒するまでもない)
ヘンリーに対面した少年は、父デュークとは対照的な、非凡さのかけらもない少年に映った。姉弟そろって美形だったが、王子という威厳はなく、ヘンリーには人の良さそうな、少し利発な程度の少年に思えた。
(まあ、ローラの弟として少しは目をかけてやるか)
ヘンリーは完全にユリウスを度外視し、適当に挨拶を交わした。
ただ、少し気にかかることがあった。ユリウスに付き従う5人の騎士達のことである。
精鋭というわけで興味を引かれたのではない。なんと表現したらいいか、違和感を覚える顔ぶれであった。
第一に、年齢層の広さ。ユリウスと同年輩の者から20過ぎに見える者。
体型もまちまちで、統一性がない。何を基準に決めたらこういう者がそろったのか、ヘンリーには理解に苦しむ集まりだった。
「後ろの騎士達は王子の護衛の者たちですか?」
言葉の端々に少々皮肉を込めてヘンリーは尋ねた。
ユリウスはそれに気付いたふうはなさそうに、平然と答えた。
「ええ。幼い頃から私の側にいる大事な者たちです」
その平凡な答えにヘンリーは全く興味を失くし、デュークとローラの会話に
心を向けた。
そうしてヘンリー王子とローラ姫の対面は滞り無く行われた−−−−−
NEXT EXIT